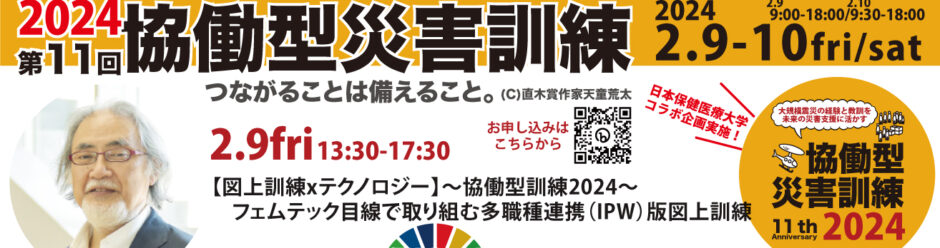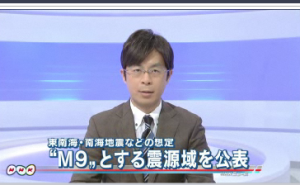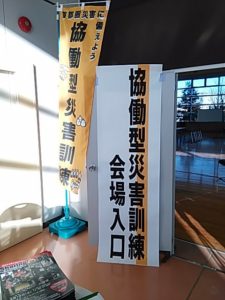 2月3日・4日、埼玉県杉戸町の「ふれあいセンターエコスポいずみ」を会場に行政・大学・医療従事者・各関係NPO、災害ボランティアが結集して「第4回協働型災害訓練」が開催された。ボランティア活動の鉄則で「鉄は熱いうちに打て」ということで熱の冷めやらぬ前に、報告と振り返りをしておこう。
2月3日・4日、埼玉県杉戸町の「ふれあいセンターエコスポいずみ」を会場に行政・大学・医療従事者・各関係NPO、災害ボランティアが結集して「第4回協働型災害訓練」が開催された。ボランティア活動の鉄則で「鉄は熱いうちに打て」ということで熱の冷めやらぬ前に、報告と振り返りをしておこう。
その前に、さすがニュースが早い、災害情報誌としては一番といえる 「リスク対策.com」が流してくれているのでそこへのリンクもしておこう。
まず参加者数は、東日本大震災から6年になろうという時期もあり、今までで一番参加者数は少なかったが、1日目に120名、2日に60名ほどの参加者があった。(スタッフ、報道など含まず)
細かな報告は長くなるので、式次第や議員さんの挨拶、アイスブレイクなどのイベントの紹介などは時間の都合で割愛させていただき、ここでは全体の振り返りと、訓練の中身ということで、1日目のISCを使ったDIG(図上訓練)と2日目のHUG(避難所運営訓練)を中心にさせていただく。
私が常々思う災害ボランティアにとって肝要な3点は「知識と体験(経験)と想像力」であるが、それをどう結び付け、活かしていけるかの学びがより明確にされた2日間だった。
まず4回目になるといろいろと見えてくるものがあり、今回は規模に関わらずに非常に勉強になって収穫の多い訓練だったこと。スタッフはじめ関係者の労をねぎらいたい。その中でも今回はTVカメラやマスコミの数も多く、国や県、防災関係の議員さん、行政職員の参加が目立ったのではないだろうか。それだ け情報が行き渡り、また関心の高さがわかった。
け情報が行き渡り、また関心の高さがわかった。
しかし、その分、以前参加の常連の顔が少なく、積み重ねて学んでいるというより初参加者への啓発や課題の提示という性格の部分が相変わらず重要であるイベントに変わりがないことはあまり進歩していないのかもしれない。 続きを読む